2024年8〜9月に読んだ本
2024/09/29 Sun Filed in: 読んだ本
・東北大学日本史研究室編「東北史講義 (古代・中世篇)」(ちくま新書)
上下2巻本。長い時間をかけて読んできたが、あまり興味が持てないテーマの論文については最後は飛ばした。私の関心は蝦夷(エミシ)の社会にある。
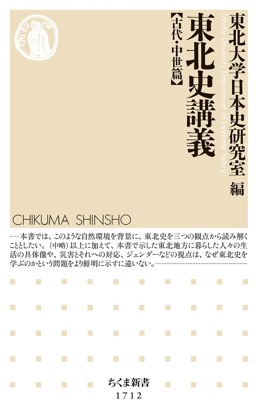
・谷川 嘉浩著「スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険」(discover)
だいぶ時間が経ったので内容をよく覚えていない。
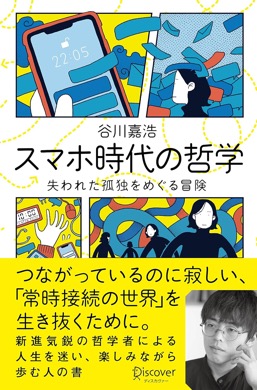
・河野 一隆著「王墓の謎」(講談社現代新書)
世界各地の王墓の造営の背景には今までの定説とは異なる発想に基づく理由があると提唱している本。これもだいぶ印象が薄れてしまった。読了後すぐに感想を書くクセがついてないので・・
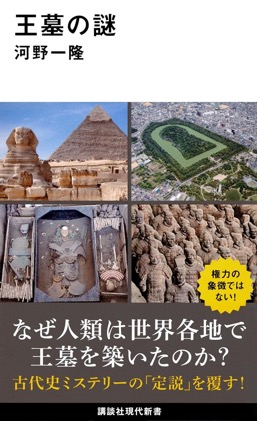
・山本 正嘉著「登山と身体の科学」(講談社ブルーバックス)
コロナ以降、本格的な登山からしばらく遠ざかっている。60代になって、もう一度登山ができる身体を作り上げたい欲求はある。それにはやはり低山を頻繁に登ることが必要なのだそうだ。もう一度筑波山の北西尾根を使ってトレーニングしようか・・でももう少し涼しくならないとダメだな、などと考えているようではそもそもダメだろう・・
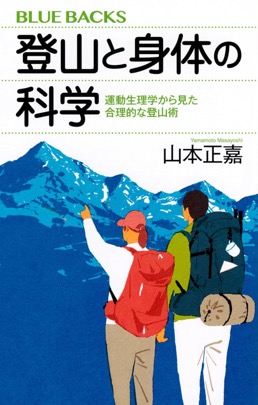
・細田 昌志著「力道山未亡人」(小学館)
力道山と結婚した太田敬子さんの現在に至るまでの人生を取材したルポ。大変面白く、短期間で読了した。相模湖の遊園地がもともとゴルフ場として力道山が購入した土地だったとか、東京スポーツの社主は児玉誉士夫だったとか、知らなかった事実が書かれていた。それにしても壮絶な人生。

・西村 カリン著「フランス人記者、日本の学校に驚く」(大和書房)
フランス人が書くと日本の制度をけなしフランスの制度を持ち上げるものだと偏見をもっていたが、著者は公平に両国の教育を見ている。
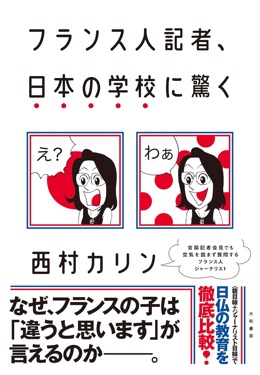
・スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著 小梅 けいと画
「戦争は女の顔をしていない 5」(講談社現代新書)
5巻目に突入。スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの本を文字で読んだことはまだないのだが、ほんとうに戦争の残酷さをえぐり出している作品だとコミックを読むだけでわかる。
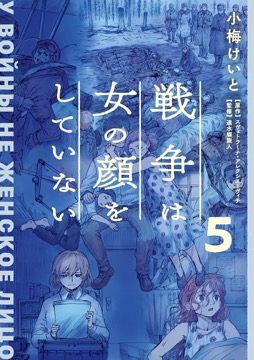
上下2巻本。長い時間をかけて読んできたが、あまり興味が持てないテーマの論文については最後は飛ばした。私の関心は蝦夷(エミシ)の社会にある。
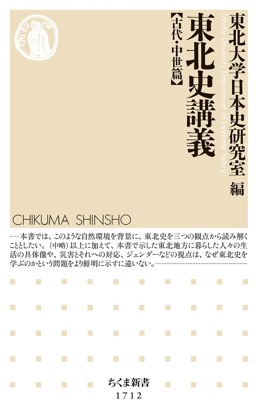
・谷川 嘉浩著「スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険」(discover)
だいぶ時間が経ったので内容をよく覚えていない。
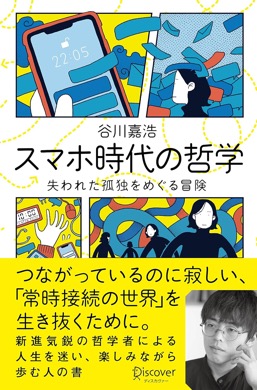
・河野 一隆著「王墓の謎」(講談社現代新書)
世界各地の王墓の造営の背景には今までの定説とは異なる発想に基づく理由があると提唱している本。これもだいぶ印象が薄れてしまった。読了後すぐに感想を書くクセがついてないので・・
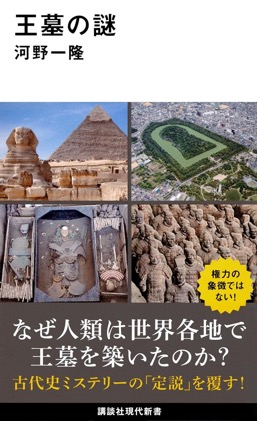
・山本 正嘉著「登山と身体の科学」(講談社ブルーバックス)
コロナ以降、本格的な登山からしばらく遠ざかっている。60代になって、もう一度登山ができる身体を作り上げたい欲求はある。それにはやはり低山を頻繁に登ることが必要なのだそうだ。もう一度筑波山の北西尾根を使ってトレーニングしようか・・でももう少し涼しくならないとダメだな、などと考えているようではそもそもダメだろう・・
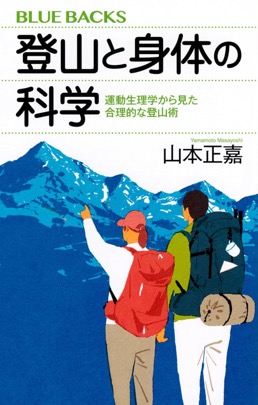
・細田 昌志著「力道山未亡人」(小学館)
力道山と結婚した太田敬子さんの現在に至るまでの人生を取材したルポ。大変面白く、短期間で読了した。相模湖の遊園地がもともとゴルフ場として力道山が購入した土地だったとか、東京スポーツの社主は児玉誉士夫だったとか、知らなかった事実が書かれていた。それにしても壮絶な人生。

・西村 カリン著「フランス人記者、日本の学校に驚く」(大和書房)
フランス人が書くと日本の制度をけなしフランスの制度を持ち上げるものだと偏見をもっていたが、著者は公平に両国の教育を見ている。
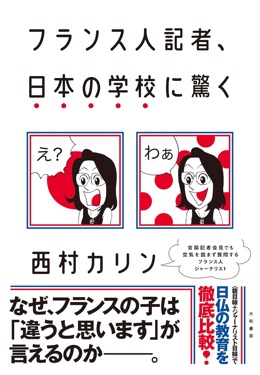
・スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著 小梅 けいと画
「戦争は女の顔をしていない 5」(講談社現代新書)
5巻目に突入。スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの本を文字で読んだことはまだないのだが、ほんとうに戦争の残酷さをえぐり出している作品だとコミックを読むだけでわかる。
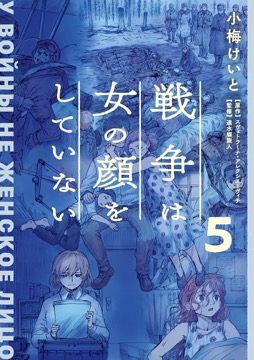
2024年6〜7月に読んだ本
2024/07/25 Thu Filed in: 読んだ本
・元沢 賀南子著「老後の家がありません-シングル女子は定年後どこに住む?」(中央公論新社)
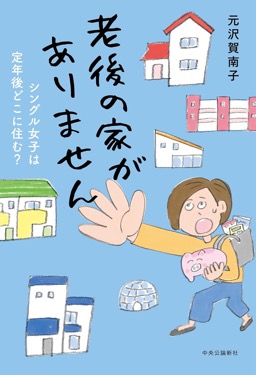
過去に何度も引っ越しを繰り返してきた著者に蓄積された、住宅探しのノウハウがまとめられていた。常識だと思っていたことが塗り替えられていくのを感じる部分があった。
・戸谷 洋志著「スマートな悪 技術と暴力について」(講談社)
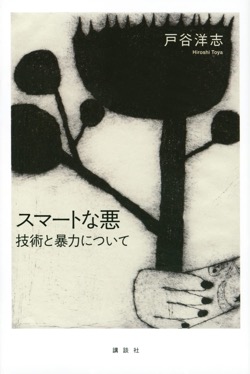
スマートフォンの「スマート」というのは「賢い」などと訳されたりするが、本来の意味はそれとは真逆の意味ダというところから説き起こして、「スマート社会」などの例に用いられるスマートさが大きな問題をはらんでいることを説いていく。「スマート社会」というキーワードで検索してみると、ほとんど何を言っているのか分からない「理想の」社会をカタカナを駆使して説明しようとしているが、ほとんど内容がない。こんな危険な言葉に踊らされて未来社会を構築していっていいのか?
・八鍬 友広著「読み書きの日本史」(岩波新書)
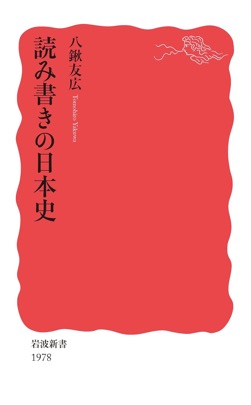
正にタイトル通り。読む、書くといった基本的リテラシーがどうやって民衆レベルにまで浸透していったのか?明治時代の学校制度発足以前に庶民の多くが読み書きに長けていた。
・磯野 真穂著「他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学」(集英社新書)

・磯野 真穂著「コロナ禍と出会い直す 不要不急の人類学ノート」(柏書房)

著者はどうやら同郷の人らしい。なかなか面白い視点で医療と人類学を結びつけて展開している。コロナ禍での人々の行動については、今から振り返ればおかしなことがいっぱいあったが、当時は無批判に従ってしまっていたことが多かったのだな、と反省した。
・著者多数「シティ・ポップ文化論」(フィルムアート社)
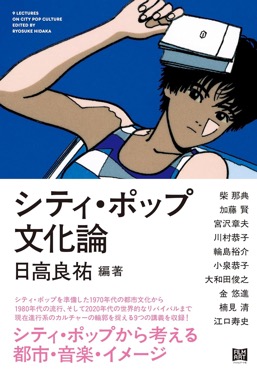
ここ数年、欧米の音楽好きから生まれて日本でもリバイバルしたシティ・ポップ。それは一体どんな音楽でどのような社会現象を起こしてきたのか?なぜシティ・ポップが日本の80年代を知らない人々に受けるのか?多くの論考が詰まっている。
・幸村 誠著「ヴィンランド・サガ(28)」(講談社 アフタヌーンコミックス)
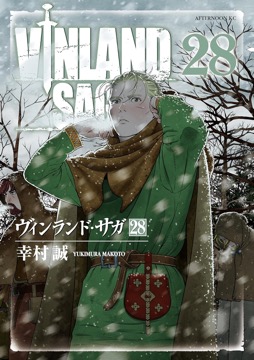
ヴィンランドに集落を形成した主人公トルフィンたちだが、先住民に疫病が伝染して対立が先鋭化する。絶対的平和主義者のトルフィンは入植した村を明け渡すことに同意するが・・・
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(2)」(小学館 ビッグコミックススペシャル)
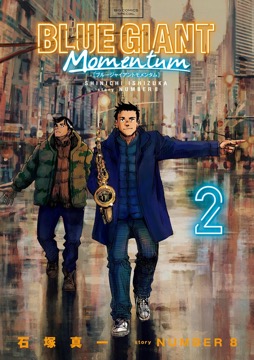
ニューヨークに乗り込んだ大たち。しかし生活は苦しく、大はアーティストビザでアルバイトをすることになる。ついにやってきたニューヨークでの初のライブセッション。ドラマーのゾッドがいい。
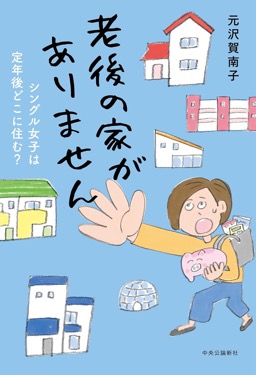
過去に何度も引っ越しを繰り返してきた著者に蓄積された、住宅探しのノウハウがまとめられていた。常識だと思っていたことが塗り替えられていくのを感じる部分があった。
・戸谷 洋志著「スマートな悪 技術と暴力について」(講談社)
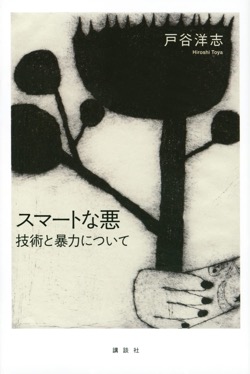
スマートフォンの「スマート」というのは「賢い」などと訳されたりするが、本来の意味はそれとは真逆の意味ダというところから説き起こして、「スマート社会」などの例に用いられるスマートさが大きな問題をはらんでいることを説いていく。「スマート社会」というキーワードで検索してみると、ほとんど何を言っているのか分からない「理想の」社会をカタカナを駆使して説明しようとしているが、ほとんど内容がない。こんな危険な言葉に踊らされて未来社会を構築していっていいのか?
・八鍬 友広著「読み書きの日本史」(岩波新書)
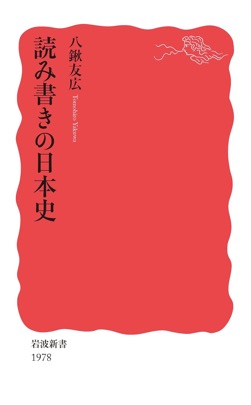
正にタイトル通り。読む、書くといった基本的リテラシーがどうやって民衆レベルにまで浸透していったのか?明治時代の学校制度発足以前に庶民の多くが読み書きに長けていた。
・磯野 真穂著「他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学」(集英社新書)

・磯野 真穂著「コロナ禍と出会い直す 不要不急の人類学ノート」(柏書房)

著者はどうやら同郷の人らしい。なかなか面白い視点で医療と人類学を結びつけて展開している。コロナ禍での人々の行動については、今から振り返ればおかしなことがいっぱいあったが、当時は無批判に従ってしまっていたことが多かったのだな、と反省した。
・著者多数「シティ・ポップ文化論」(フィルムアート社)
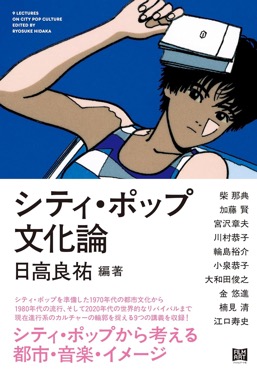
ここ数年、欧米の音楽好きから生まれて日本でもリバイバルしたシティ・ポップ。それは一体どんな音楽でどのような社会現象を起こしてきたのか?なぜシティ・ポップが日本の80年代を知らない人々に受けるのか?多くの論考が詰まっている。
・幸村 誠著「ヴィンランド・サガ(28)」(講談社 アフタヌーンコミックス)
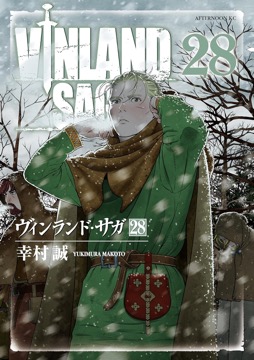
ヴィンランドに集落を形成した主人公トルフィンたちだが、先住民に疫病が伝染して対立が先鋭化する。絶対的平和主義者のトルフィンは入植した村を明け渡すことに同意するが・・・
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(2)」(小学館 ビッグコミックススペシャル)
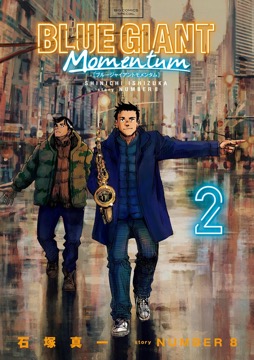
ニューヨークに乗り込んだ大たち。しかし生活は苦しく、大はアーティストビザでアルバイトをすることになる。ついにやってきたニューヨークでの初のライブセッション。ドラマーのゾッドがいい。
2024年4〜5月に読んだ本
2024/06/02 Sun Filed in: 読んだ本
今回も著者名・書名・出版社名と本の表紙のみ掲載する。
それなりに面白い本ばかりだったのだが、内容まで踏み込んで書評を書くまでの余裕がない。
・若林 正丈著「台湾の歴史」(講談社学術文庫)
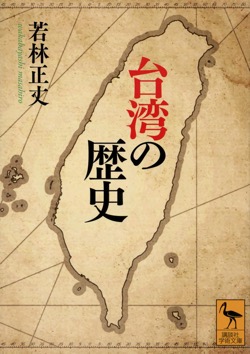
・広野 真嗣著「奔流 コロナ『専門家』はなぜ消されたのか」(講談社学術文庫)
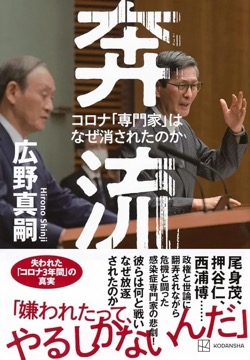
・宮地 美陽子著「首都防衛」(講談社現代新書)
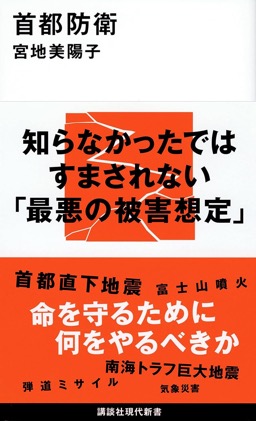
・信濃川 日出雄著「山と食欲と私18」(バンチコミックス)

・ヤマザキ マリ著「続 テルマエ・ロマエ1」(ジャンプコミックスDIGITAL)
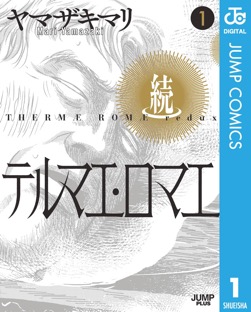
それなりに面白い本ばかりだったのだが、内容まで踏み込んで書評を書くまでの余裕がない。
・若林 正丈著「台湾の歴史」(講談社学術文庫)
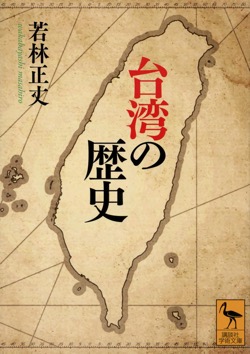
・広野 真嗣著「奔流 コロナ『専門家』はなぜ消されたのか」(講談社学術文庫)
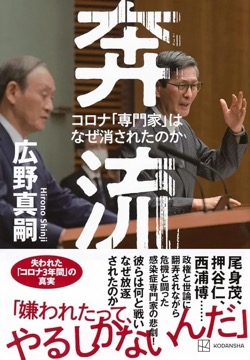
・宮地 美陽子著「首都防衛」(講談社現代新書)
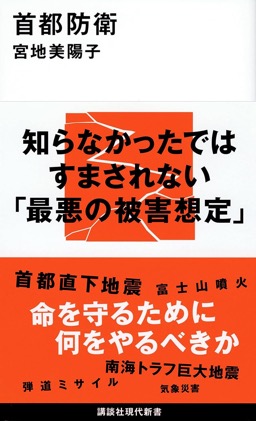
・信濃川 日出雄著「山と食欲と私18」(バンチコミックス)

・ヤマザキ マリ著「続 テルマエ・ロマエ1」(ジャンプコミックスDIGITAL)
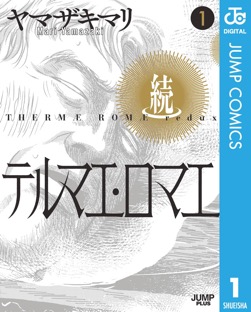
2024年1月下旬から3月に読んだ本
2024/03/24 Sun Filed in: 読んだ本
最近、なかなか本の文言に集中できず、読了しても読後感が明確につくれていない。時間が経つと読後評を書くのも面倒になってしまう。
以下に挙げた本はすべて電子書籍で購入したが、上の空のうちに電子書籍のページを繰っていき、だんだん飽きてきて内容をしっかり理解しないままに読了にしてしまう傾向が強い。
・山本 直輝著「スーフィズムとは何か」(集英社新書)

・斎藤 幸平著「コモンの『自治』論」(集英社)
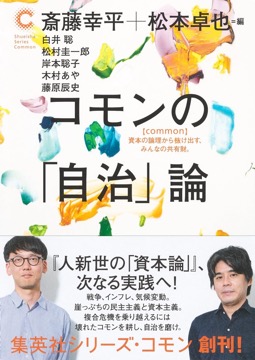
・鹿毛 敏夫著「世界史の中の戦国大名」(講談社現代新書)
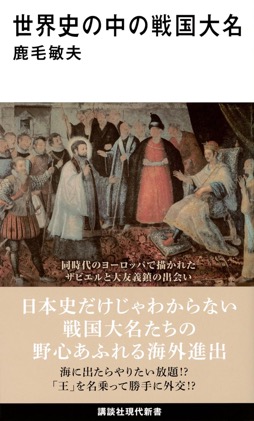
・中村 隆文著「なぜあの人と分かり合えないのか 分断を乗り越える公共哲学」(講談社選書メチエ)
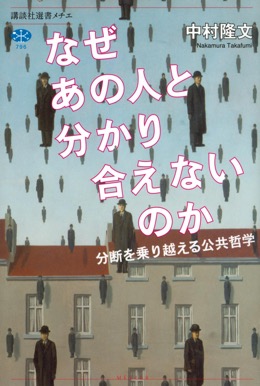
・永嶺 重敏著「読書国民の誕生 近代日本の活字メディアと読書文化」(講談社学術文庫)
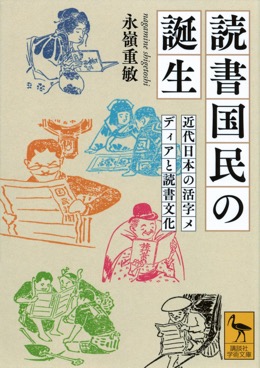
・石塚 真一著「BLUE GIANT EXPLORER(9)」(ビッグコミックス)
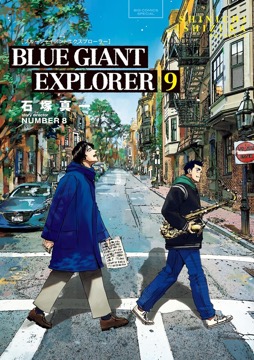
ジャズ漫画、「ブルージャイアント」のアメリカ編最後の巻。ニューヨークへ行く前に立ち寄ったボストンのバークリー音楽院に、JASSのピアノマン、沢辺が在学していた。沢辺と大が出会うシーンからもう感涙にむせぶ。沢辺が作曲した体で発表された現実のジャズマン、ジュリアス・ロドリゲスの「MOMENTUM」が配信されているが、この曲も実にカッコいい。ヘビーローテーション中。
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(1)」(ビッグコミックススペシャル)

ついに大が率いるジャズバンド、DAI MIYAMOTO MOMENTUMがニューヨークに乗り込む。しかしここでも下積みの生活が始まる。ジャズの本場ニューヨークで大たちはどのようにのし上がっていくのか?これからも、目が離せない。
以下に挙げた本はすべて電子書籍で購入したが、上の空のうちに電子書籍のページを繰っていき、だんだん飽きてきて内容をしっかり理解しないままに読了にしてしまう傾向が強い。
・山本 直輝著「スーフィズムとは何か」(集英社新書)

・斎藤 幸平著「コモンの『自治』論」(集英社)
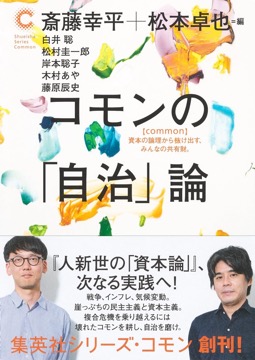
・鹿毛 敏夫著「世界史の中の戦国大名」(講談社現代新書)
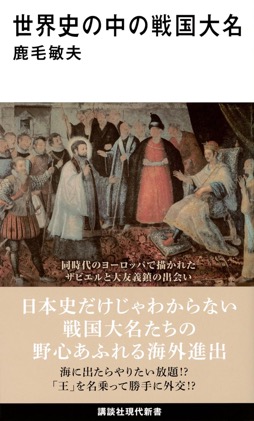
・中村 隆文著「なぜあの人と分かり合えないのか 分断を乗り越える公共哲学」(講談社選書メチエ)
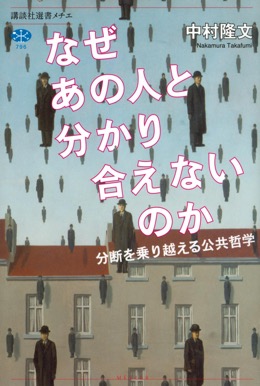
・永嶺 重敏著「読書国民の誕生 近代日本の活字メディアと読書文化」(講談社学術文庫)
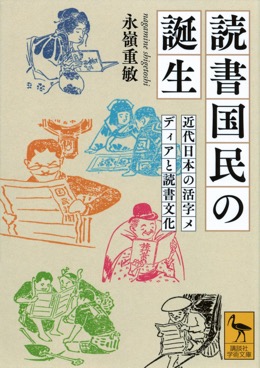
・石塚 真一著「BLUE GIANT EXPLORER(9)」(ビッグコミックス)
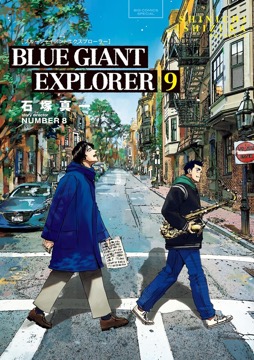
ジャズ漫画、「ブルージャイアント」のアメリカ編最後の巻。ニューヨークへ行く前に立ち寄ったボストンのバークリー音楽院に、JASSのピアノマン、沢辺が在学していた。沢辺と大が出会うシーンからもう感涙にむせぶ。沢辺が作曲した体で発表された現実のジャズマン、ジュリアス・ロドリゲスの「MOMENTUM」が配信されているが、この曲も実にカッコいい。ヘビーローテーション中。
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(1)」(ビッグコミックススペシャル)

ついに大が率いるジャズバンド、DAI MIYAMOTO MOMENTUMがニューヨークに乗り込む。しかしここでも下積みの生活が始まる。ジャズの本場ニューヨークで大たちはどのようにのし上がっていくのか?これからも、目が離せない。
2023年11月〜2024年1月中旬までに読んだ本
2024/01/21 Sun Filed in: 読んだ本
・筒井 康隆著「カーテンコール」(新潮社)
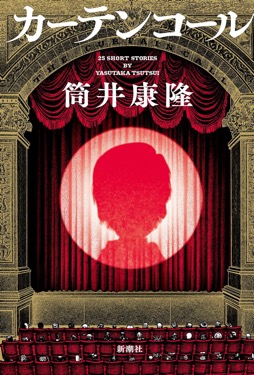
筒井康隆の「最後の作品集」という帯に惹かれて久しぶりに新館単行本そのものを購入。短編集だが、少し枯れた筒井康隆の文章があった。最後の方の短編の印象が残る。
・伊藤 彰彦著「映画の奈落 北陸代理戦争事件」(新潮社)
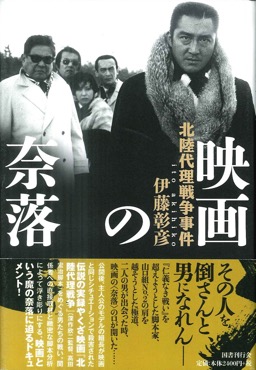
表紙の通り、東映ヤクザ映画の中に副題の「北陸代理戦争」という映画があった。一回観たことがある。実在の人物をヒントに、脚本家高田宏治がストーリーを創り上げたものだ。映画のシーンに喫茶店での襲撃があるのだが、映画封切後に実際に暴力団員の抗争が喫茶店を舞台にしてあった。映画が先行し実際の事件が後追いで生じたという衝撃的な事件だった。それらを追った本である。著者の本はこれで三冊くらい読んだが、この本については最後の方の著者の思い入れたっぷりの文章に少しついていけなくなった。
・内田 樹・白井 聡著「新しい戦前 この国の"いま"を読み解く」(朝日新書)
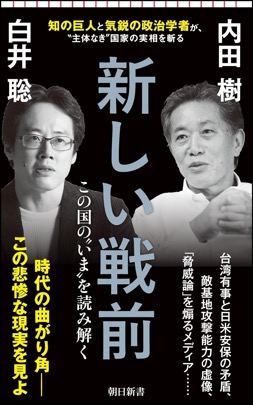
対談集である。読んでいるとこの国は本当にまずい状況に置かれていることがわかる。裏金を作って懐に納め、特捜部からの追及があると派閥解消などという弥縫策で済ませようとしている連中にかじ取りを任せていることはさらに危険な状況の生成に繋がらないのか?
・大澤 真幸・斎藤 幸平著「未来のための終末論」(朝日新書)

これまた大澤と斎藤の対談集。しかし対談そのものは本の4割で終わってしまい、三田宗介の論の紹介、ブックリスト、最後に大澤の論文が後半を占めるという不思議な構成になっていた。それなら別の本にすればいいのに。大澤の論は一般人には難しくて(衒学的で)なかなか理解ができない。
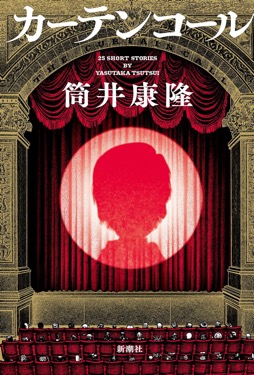
筒井康隆の「最後の作品集」という帯に惹かれて久しぶりに新館単行本そのものを購入。短編集だが、少し枯れた筒井康隆の文章があった。最後の方の短編の印象が残る。
・伊藤 彰彦著「映画の奈落 北陸代理戦争事件」(新潮社)
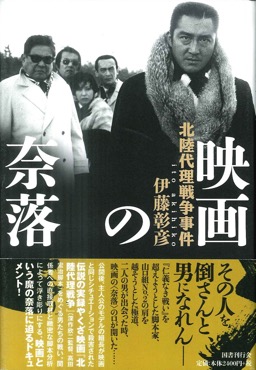
表紙の通り、東映ヤクザ映画の中に副題の「北陸代理戦争」という映画があった。一回観たことがある。実在の人物をヒントに、脚本家高田宏治がストーリーを創り上げたものだ。映画のシーンに喫茶店での襲撃があるのだが、映画封切後に実際に暴力団員の抗争が喫茶店を舞台にしてあった。映画が先行し実際の事件が後追いで生じたという衝撃的な事件だった。それらを追った本である。著者の本はこれで三冊くらい読んだが、この本については最後の方の著者の思い入れたっぷりの文章に少しついていけなくなった。
・内田 樹・白井 聡著「新しい戦前 この国の"いま"を読み解く」(朝日新書)
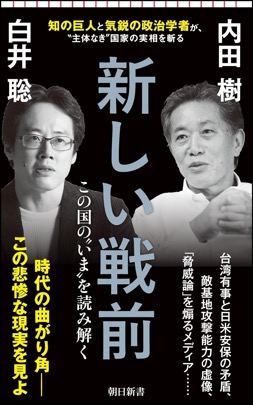
対談集である。読んでいるとこの国は本当にまずい状況に置かれていることがわかる。裏金を作って懐に納め、特捜部からの追及があると派閥解消などという弥縫策で済ませようとしている連中にかじ取りを任せていることはさらに危険な状況の生成に繋がらないのか?
・大澤 真幸・斎藤 幸平著「未来のための終末論」(朝日新書)

これまた大澤と斎藤の対談集。しかし対談そのものは本の4割で終わってしまい、三田宗介の論の紹介、ブックリスト、最後に大澤の論文が後半を占めるという不思議な構成になっていた。それなら別の本にすればいいのに。大澤の論は一般人には難しくて(衒学的で)なかなか理解ができない。
